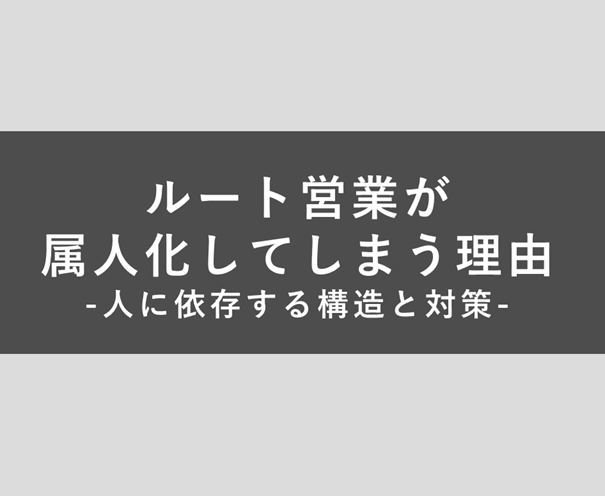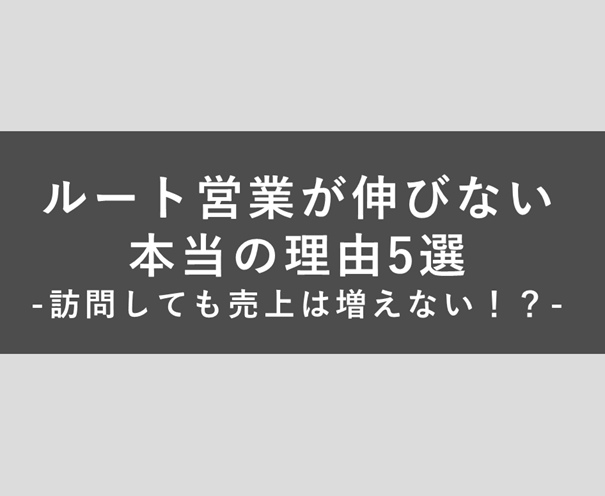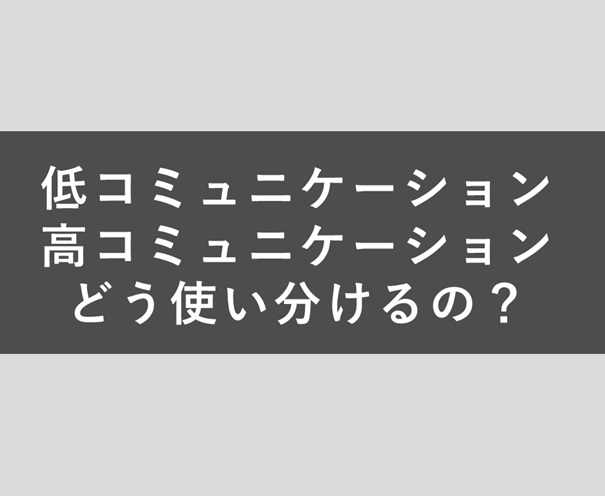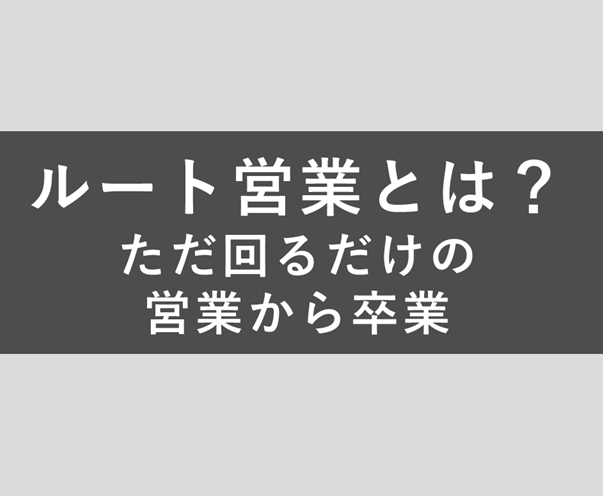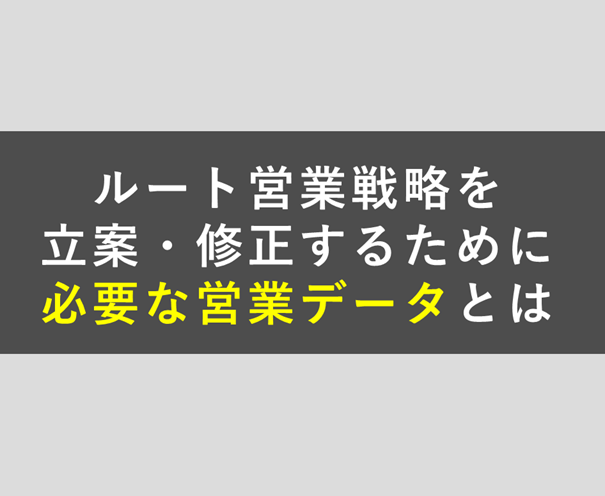マイクロorザックリマネジメント、どちらがいいのか
部下のマネジメントで壁にぶつかった際に必ず頭をよぎるのが・・・
「マイクロマネジメントに変えてみるか」もしくは「ザックリ(放任)マネジメント」に変えてみる
というマネジメント方針の変更です。
※マクロマネジメントが表現としてしっくり来ないのでザックリマネジメントと言い換えてます。
どちらも一長一短があり、どちらが正しいという正解はありません。
ただ、「どちらが合っているのか」についてはマネージャーと部下のキャラクター(適性)によって存在するはずであると僕は考えています。
マネージャーが・・・マイクロ or ザックリ
部下が・・・・・・・マイクロ or ザックリ
この掛け合わせて組織やチームのパフォーマンス水準をある程度、高めることができます。
(1)マネージャーがマイクロ ✕ 部下がマイクロ
このマネジメント体制ならばお互いストレスなく、そして業務の漏れやミスが減っていくことが見込まれるでしょう。
マネージャーからすれば「指示したことをしっかりやってくれる」
部下からすれば「面倒見が良いし、言った通りにしておけば間違いないから助かる」
といった具合に互いの信頼は強固になっていき、業務水準は高まっていくはずです。
一方でデメリットがあって、部下が細かな指示がないと動けないビジネスパーソンになってしまう恐れがあります。
(2)マネージャーがザックリ ✕ 部下がザックリ
こちらも互いのストレスは少ないはずです。
ただし、お互いのザックリが噛み合えば・・・という前提条件付きです。
マネージャーはザックリとした指示を行うものの、部下の成果や行動に対して「この程度の結果は出してくれるだろう」と期待しています。
ところが思ったような、というより想定を下回るような成果だった場合は
マネージャー「どうしてこれくらいのことも出来ないのか・・・」
部下「指示がザックリしすぎてるから、そりゃ出来ないよ・・・」
とお互い不満を抱きかねません。
そしてチームとして低パフォーマンスになってしまっているのはこのケースが多く見られます。
部下が新人ではなく、一定の経験を積んでいればお互いのザックリ具合がうまく噛み合う場合が多いです。
(3)マネージャーがマイクロ ✕ 部下がザックリ
マネージャーも部下もお互いに最もストレスがかかるのはこのパターンです。
が、お互いの成長が最も期待できるのもこのパターンです。
マイクロマネジメントが悪い意味で使われる時はこの(3)のパターンに該当する場合だと僕は考えています。
この場合は、ザックリタイプの部下が事細かに指示してくるマネージャーをディスる意味合いで利用されています。
部下からすると「マネージャーはオレ(私)のことを信頼してくれていない・・・」というストレスを抱え、
マネージャーからすると「なんであんな適当なスタンスで仕事ができるのか・・・」と不安を抱かせる関係です。
お互いがマイクロ(ザックリ)であることを認識して、どんな成果を期待して(され)ているのかを理解することで能力の幅が広がります。
理解し合えれば・・・
マネージャーは指示の出し方や指導育成技法の引き出しが増え、
部下は業務の請け方や進め方が慎重で丁寧になっていきます。
(4)マネージャーがザックリ ✕ 部下がマイクロ
社員(部下)が辞めていくことが多いパターンです。
部下側がマネージャーの指示を咀嚼できないと、行動に移せないなどといった問題が起こります。
「強いチームはNo.2が優秀」というのはまさにこれだと思います。
マネージャーはザックリだけど求心力があるタイプで、No.2がマネージャーの意図を汲み取ってマイクロ部下との架け橋になっているチームです。
古いドラマですが「リッチマン、プアウーマン」というドラマで井浦新さんが演じていた役が優秀なNo.2のイメージです。
マネージャーのザックリを翻訳できる人がチームに居ないと4の場合はうまく回らないので注意が必要です。
4つのパターンを挙げてみましたがチーム編成に最適解は無いことがわかります。
ただ最大出力を発揮する掛け合わせはあるのです。
4つの中から自社にとっての最大出力が望めそうな掛け合わせを見つけ、弱点を補完するというのが組織マネジメントです。
個人的には3のパターンが好きです。
が、以前、勤めていた会社にマイクロヒステリック超短気マネージャーが隣のチームに居て、3ヶ月で5人くらい部下が辞めていったのを見ているので何とも言えません(汗)